国民民主党の榛葉幹事長が記者会見で、自民党の麻生氏から漫画『ひらばのひと』(著:久世番子)の7巻を借りようとしたエピソードを披露し、話題になりましたね。「7巻がなくて残念!」と語る榛葉氏の熱意に、「一体どんな漫画なんだろう?」と興味を持った方も多いのではないでしょうか。
この記事では、政治家も夢中になる『ひらばのひと』の魅力を深掘りします。講談という珍しい題材を扱った本作のあらすじ、主要登場人物、そして作者・久世番子先生の魅力まで、徹底解説!あなたもきっと、『ひらばのひと』の世界に引き込まれるはずです。

『ひらばのひと』は「講談」の世界を描く!久世番子先生の異色作
独特の節で読む軍記物の勇壮な場面を、講談で「修羅場〈ひらば〉」と呼ぶーー。
落語家との認知度の差は歴然、絶滅危惧「職」とまで言われる講談師。二ツ目の女流講談師・龍田泉花の未来は視界不明瞭! 唯一の弟〈おとうと〉弟子・泉太郎の率直(不敵?)過ぎる言動にもヤキモキしっぱなしーー。でも「講談」の深い魅力と、師匠をはじめ人間臭い周囲の人々に支えられながら、姉弟〈きょうだい〉弟子2人は、ダンジョンだらけの「芸の道」をよじ登っていく!
引用元:講談社コミックプラス
『ひらばのひと』は、漫画家・久世番子先生が描く、講談を題材にした日本の漫画作品です。講談界の第一人者である六代目神田伯山師匠が監修を務めており、その本格的な描写が大きな魅力となっています。落語を扱った漫画は多いですが、講談に特化した作品は非常に珍しく、その独自性で注目を集めています。
本作は、2020年11月号から『月刊モーニングtwo』で連載がスタートしました。その後、同誌の紙版休刊に伴い『モーニング』へと移籍し、2023年8号から2025年28号まで連載される予定です。講談社の名前の由来が講談の速記本に発展したことに因むというのも、興味深い縁ですね。
そもそも「講談」とは?
講談とは、釈台と呼ばれる机の前に座り、張扇(はりおうぎ)で調子を取りながら、軍記物語や史実に基づいた読み物を読み上げる日本の伝統芸能です。『ひらばのひと』では、この奥深い講談の世界が初心者にも分かりやすく、そして魅力的に描かれています。
『ひらばのひと』のあらすじ:講談師たちの熱き修行と人間ドラマ
物語の舞台は、かつての隆盛からは遠のき、絶滅危惧種とも言われる現代の講談界です。主人公は、講談への並々ならぬ情熱を燃やす若者、龍田泉太郎(たつた せんたろう)。彼は前座2年目の24歳で、師匠・龍田錦泉のもとで日々修行に励んでいます。
女性講談師が多数を占める現代において、泉太郎は久々の男弟子として、古参のファンからも大きな期待を寄せられています。教育係である二ツ目の龍田泉花(たつた せんか)をはじめ、多くの個性豊かな女性講談師たちに囲まれながら、泉太郎は飄々としつつも真摯に芸の道を探求していきます。彼の修行の日々と並行して、7年前に焼失した幻の講釈場「音羽亭」の謎も物語の重要な要素として描かれ、登場人物たちの過去や絆が深く掘り下げられていきます。

『ひらばのひと』主要登場人物紹介
- 龍田 泉太郎(たつた せんたろう):講談好きが高じて講談師の世界へ。龍田錦泉の末弟子で、前座2年目の若手。普段は無頓着で飄々としていますが、講談への情熱は人一倍。7年前に消えた講釈場「音羽亭」の謎を追う中心人物です。
- 龍田 泉花(たつた せんか):二ツ目の女性講談師で、泉太郎の教育係。34歳。久々の男弟子である泉太郎に、期待と厳しさをもって接します。一般人の夫との生活も描かれ、講談師としての顔と女性としての葛藤が魅力です。
- 龍田 錦泉(たつた きんせん):泉太郎と泉花の師匠。80歳のベテラン講談師で、錦泉一門を率いる重鎮。生まれつきの吃音を講談で克服した過去を持ち、その芸は常に聴衆を惹きつけます。
- 玉野井 鹿山(たまのい ろくざん):独演会を満席にする実力派講談師。真打昇進前は玉野井一鹿。自分に厳しくストイックな人物ですが、実は音羽亭の全焼事件に深く関わっており、物語の鍵を握る存在です。
これらの個性豊かな登場人物たちが織りなす人間ドラマは、『ひらばのひと』の大きな見どころ。華やかな舞台の裏側で、講談という伝統芸能を支え、未来へと繋ごうとする彼らの熱い思いが、読者の心を打ちます。

作者:久世番子先生の魅力と代表作
『ひらばのひと』の作者である久世番子(くぜ ばんこ)先生(1977年12月5日生まれ、愛知県出身)は、その独自の視点と表現で多くの読者を魅了する漫画家です。
漫画家としてのキャリア
2000年に『月刊ウィングス』でデビュー。初期には『少年愛の世界』などの作品を発表しています。
エッセイコミックの先駆者『暴れん坊本屋さん』
久世先生の名を広く知らしめたのは、2005年から連載されたエッセイコミック『暴れん坊本屋さん』です。長年の書店アルバイト経験をもとに、本屋の舞台裏や出版業界の知られざる内情(返品制度や買い切りなど)を詳細かつユーモラスに描き、多くの読者から支持を得ました。この作品は『朝日新聞』などでも書評が掲載されるなど、社会現象を巻き起こしました。
多岐にわたる作品世界
2006年末に書店を退職して漫画家業に専念してからは、さらにその才能を開花させています。
- 『神は細部に宿るのよ』:日常の「あるある」を哲学的に、時にコミカルに描く。
- 『よちよち文藝部』シリーズ:読書家としての視点から、文芸作品をユニークに紹介。
- 『パレス・メイヂ』:明治時代を舞台にした歴史フィクション。
このように、久世番子先生はエッセイ、フィクション、そして今回ご紹介した『ひらばのひと』のような伝統芸能をテーマにした作品まで、幅広いジャンルで活躍しています。どの作品も、久世先生ならではの鋭い観察眼と温かい視点が光ります。

まとめ:『ひらばのひと』で講談の奥深さに触れてみよう!
国民民主党の榛葉幹事長も絶賛する漫画『ひらばのひと』は、知られざる講談の世界を舞台に、若き講談師たちの成長と人間ドラマを描いた久世番子先生の魅力的な作品です。六代目神田伯山師匠監修の本格的な内容ながら、漫画ならではの面白さで、読者は自然と講談の奥深さに引き込まれることでしょう。
講談に興味がある方はもちろん、まだ触れたことがない方にも、ぜひ一度読んでいただきたい一冊です。『ひらばのひと』を読んで、あなたも講談の世界に足を踏み入れてみませんか?
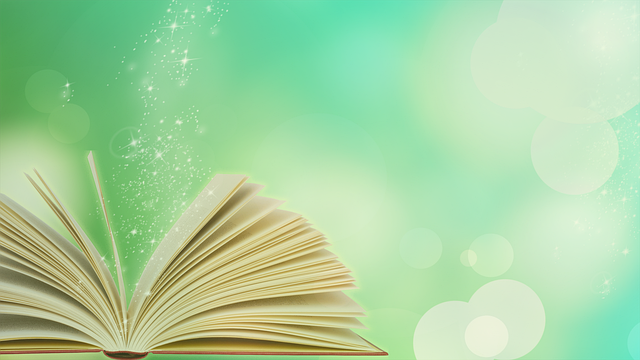


コメント